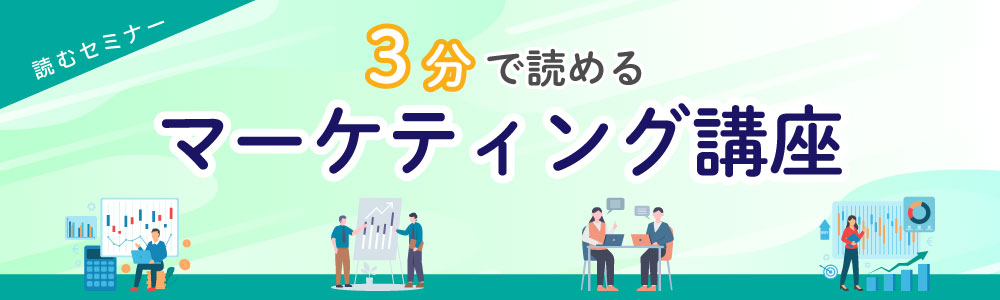
"3分で読める"マーケティングに関するコラムの第8回です。
是非ご覧ください。
≪ 本コラムの記事一覧はこちら
【第8回】ファンを育てるコミュニティの力:SNSのマーケティング
SNSは会話の場所
デジタルマーケティングの中でも、特に重要な位置を占めるのがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)マーケティングです。
多くの企業がSNSを活用していますが、その本質を単なる「広告を出す場所」と捉えていると、大きな機会を逃すことになります。
SNSの真価は、企業と顧客、あるいは顧客同士が「会話」をし、関係性を築き、ブランドの「ファン」が生まれるコミュニティを育む場である点にあります 。
各プラットフォームには独自の文化と強みがあります。
- X(旧Twitter)
リアルタイム性、情報の拡散力に優れ、顧客との迅速なコミュニケーションやカスタマーサポートに適しています。 - Instagram
ビジュアル中心のプラットフォームで、ブランドの世界観やライフスタイルを伝えるのに最適です。インフルエンサーマーケティングの主戦場でもあります。 - TikTok
短尺動画によるエンターテインメント性が高く、若年層を中心にトレンドが生まれやすいのが特徴です 。 - Facebook
幅広い年齢層が利用しており、実名性が高いため、地域密着型のビジネスや深いコミュニティ形成に向いています。 - LINE
クーポン配布や個別メッセージなど、既存顧客との直接的でクローズドなコミュニケーションを通じて、ロイヤルティを高めるのに強力なツールです 。
SNSマーケティング成功の鍵
成功している企業は、単に情報を発信するだけでなく、以下のような戦略を巧みに用いています。
エンゲージメントの重視
一方的に投稿するのではなく、質問を投げかけたり、アンケートを実施したり、
コメントに丁寧に返信したりすることで、双方向のコミュニケーションを創出します。
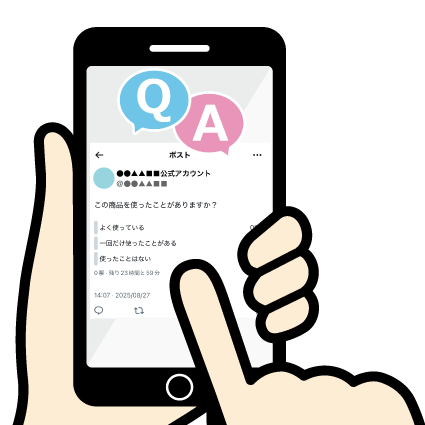
UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用
「#(ハッシュタグ)」を付けて投稿してもらうキャンペーンなどを通じて、ユーザー自身にコンテンツを作ってもらいます。
これは、企業発信の情報よりも信頼性の高い「口コミ(ソーシャルプルーフ)」として機能します。
例えば、アサヒビールが自社製品と一緒に写真を投稿してもらうキャンペーンなどがこれにあたります。

インフルエンサーマーケティング
自社のターゲット層から信頼されているインフルエンサーと協業します。
近年では、フォロワー数が膨大なメガインフルエンサーよりも、特定の分野で熱心なファンを持つマイクロ・ナノインフルエンサーの方が、高いエンゲージメントを生むとして注目されています。
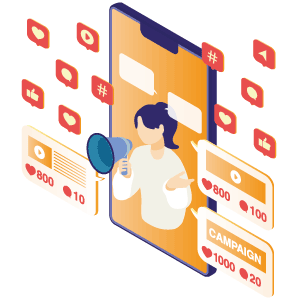
キャンペーンの実施
プレゼント企画やコンテストは、フォロワー増加やエンゲージメント向上のための効果的な手段です。
例えば、リプトンが行ったリポストキャンペーンや、スシローと人気ゲーム「モンスターハンター」のコラボキャンペーンは、多くの参加者を集め、話題を呼びました。
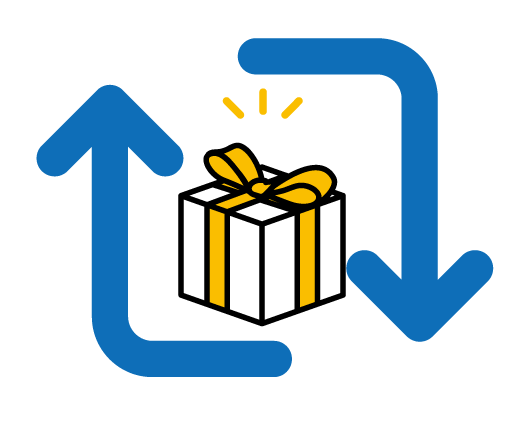
事例に学ぶ「価値提供」の姿勢
- ドミノ・ピザ
Facebookで「今夜は料理したくない時だってあるよね」といった、ユーザーの気持ちや状況に寄り添ったタイムリーな投稿を行い、共感を呼んでいます 。 - ライオン(スーパーNANOX) ※現在はNANOX one公式アカウント
Twitterで「#NANOX相談所」というハッシュタグを使い、洗濯に関する役立つ豆知識を発信。
現在はハッシュタグを新商品名等に変更しながらも、同じテーマで情報発信を続けています。
これにより、単なる洗剤の売り手ではなく、「洗濯の悩みを解決してくれる専門家」という信頼を勝ち取っています 。
これらの事例からわかるのは、SNSにおける真の通貨は「フォロワー数」ではなく「信頼」であるということです。
フォロワーが100万人いても無関心な層であるより、1000人でも熱心なファンである方が、ビジネスにとってはるかに価値があります。
SNSのアルゴリズムも、単なるフォロワー数よりエンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど)を重視する傾向にあり、これは本質的な価値提供と信頼関係の構築が評価されることを意味しています 。
さらに、SNSはマーケティング、カスタマーサービス、製品開発の境界線を曖昧にします。
顧客からのクレームへの公開返信は、カスタマーサービスであると同時に、企業の姿勢を示すマーケティング活動にもなります。
コメント欄での新機能の提案は、貴重な製品開発のフィードバックです。
SNSを効果的に活用するには、部門間の壁を取り払い、顧客の声をリアルタイムで経営に活かす、統合的な組織体制が求められるのです。
第9回は、9月11日更新予定です。