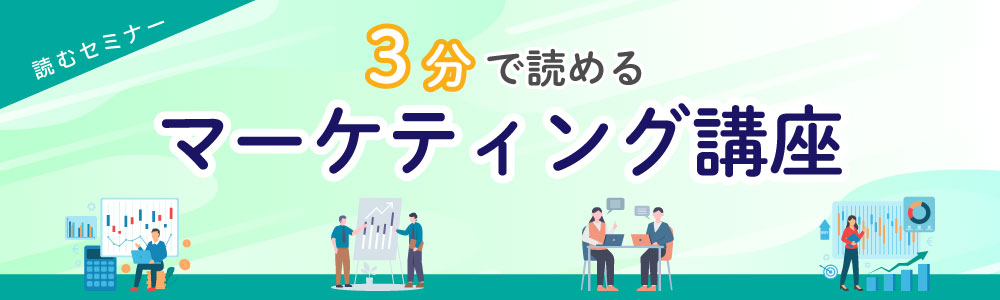
"3分で読める"マーケティングに関するコラムです。
是非ご覧ください。
【第1回】マーケティングとは何か?
はじめに:マーケティングへのよくある誤解
マーケティングという言葉を聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、テレビCMやWeb広告、あるいは熱心な営業活動かもしれません。
しかし、これらはマーケティング活動の「一部」ではあっても、そのすべてではありません。
マーケティングの本質は、単なる宣伝や販売促進活動だけではなく、より広範囲な戦略的な概念です。
まずこの最も一般的な誤解を解き、マーケティングの定義と目的をご説明します
マーケティングの理想:「販売を不要にする」こと
経営学の大家ピーター・ドラッカーは、「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」という有名な言葉を残しました 。
これは、顧客とそのニーズを深く理解し、顧客に完璧に合った製品やサービスを提供できれば、企業が必死に「売り込まなくても」、製品は自然と売れていく状態をつくれる、という意味です。
これが目指すべきゴールと言えるでしょう。
この理想をより現実的な言葉で表現したのが、「売れる仕組みづくり」というコンセプトです 。
これは、営業担当者が個人の努力で必死に顧客を探し回るのではなく、顧客の側から自然と商品やサービスに興味を持ち、購買に至るまでの一連の流れ、つまり「仕組み」を構築することを目指します。
例えば、銀行を例にとると,多くの人々はATMの利用や公共料金の支払いのために、特に勧誘されなくても自ら銀行を訪れます。
そこに来店した顧客に対して、「投資信託はいかがですか?」と提案する機会が生まれます。
これは、まず「集客の仕組み」が確立されているからこそ可能な販売活動です 。
このように、顧客を惹きつけ、関係を構築し、自然な形で購買へと導くプロセス全体を設計し、管理することが、マーケティングそのものなのです。
現代のマーケティング定義:「共創」というキーワード
時代と共に、マーケティングの理解も変化しています。
かつては「良いモノを作れば売れる」という製品中心の考え方が主流でした 。
テレビや新聞といったマスメディアの影響力が絶大で、需要が供給を上回る「売り手市場」だった時代には、いかに多くの人に自社製品を知ってもらうか、が企業の最大の関心事でした。
しかし、市場が成熟し、インターネットの普及によって消費者が力を持つようになると、企業は顧客のニーズに寄り添う「顧客中心」の考え方へとシフトしました 。
そして現代、企業を取り巻く環境はさらに複雑化しています。
2024年に日本マーケティング協会が34年ぶりに刷新した定義では、マーケティングを「顧客、クライアント、パートナー、そして社会全体にとって価値のあるオファーを創造し、伝達し、提供し、交換するための活動、一連の制度、そしてプロセス」と定義づけしなおしています。
引用:公益社団法人日本マーケティング協会
(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。
(2024年1月25日改訂)
ここでの重要な変化は、マーケティングの主体が企業だけでなく、顧客や社会といったステークホルダー全体との「共創」へと移行した点です 。
単に競合に勝つことや利益を追求するだけでなく、社会的な課題や持続可能性にも配慮し、顧客と共に新しい価値を創り出していく活動こそが、現代のマーケティングに求められる姿なのです。
この変化を理解することは、なぜ現代のマーケティング手法がこれほど多岐にわたり、統合的なアプローチを必要とするのかを理解する上で不可欠です。
それは、ビジネスと社会そのものの変化に対応した必然的な結果なのです。
第2回は、7月17日更新予定です。