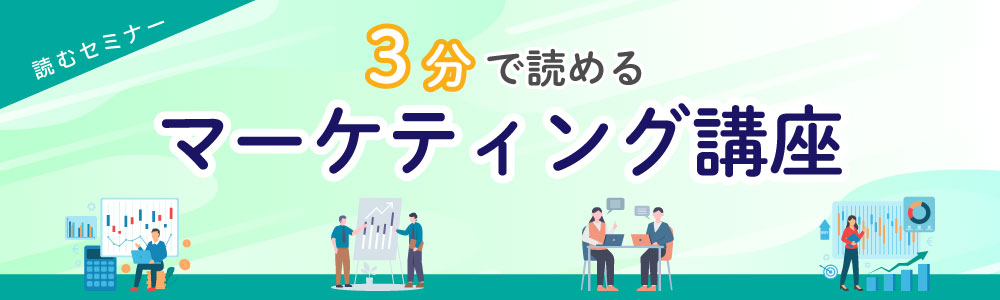
"3分で読める"マーケティングに関するコラムの第3回です。
是非ご覧ください。
≪ 本コラムの記事一覧はこちら
【第3回】戦場を知る:3C分析による環境分析
なぜフレームワークを使うのか
ここまでの講座で、マーケティングの心構えと顧客価値という中心概念を学びました。
ここからは、より実践的な思考ツールである「フレームワーク」を活用していきます。
フレームワークとは
物事を整理し、分析するための「型」や「枠組み」のことです。
これを用いることで、思考の抜け漏れを防ぎ、複雑な状況を構造的に理解し、チーム内で共通の言語を持つことができるようになります。
今回紹介する 「3C分析」 は、あらゆるマーケティング戦略の出発点となる最も基本的なフレームワークです。
3C分析とは
3C分析とは、自社を取り巻く事業環境を3つの「C」の視点から分析する手法です。
その目的は、市場における成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出し、自社の戦略を立てるための土台を築くことにあります 。

- Customer(市場・顧客)
市場の規模はどれくらいか、成長しているか。顧客は誰で、何を求めているのか。 - Competitor(競合)
どのような競合が存在し、その強み・弱みは何か。競合はどのような戦略をとっているか。 - Company(自社)
自社の強み・弱みは何か。どのような資源(人、モノ、金、技術)を持っているか。
分析の「順番」がすべてを決める
3C分析において最も重要なポイントは、分析を行う「順番」です。
必ず「市場・顧客 → 競合 → 自社」の順で分析を進めます。
なぜなら、この順番は、思考のバイアスを防ぎ、客観的な戦略を立てるための鉄則だからです。
多くの企業は、無意識のうちに「自社(Company)」から分析を始めてしまいます。
「我々の製品にはこんなに素晴らしい技術がある」といった内向きの視点です。
しかし、その技術が顧客に全く求められていなかったり、競合がそれ以上のものをより安く提供していたりすれば、その「強み」は市場では何の意味も持ちません。
まず「市場・顧客(Customer)」を分析することで、顧客が何を価値と感じているのか、市場のルールがどうなっているのかを理解します。
次に「競合(Competitor)」を分析し、その市場で他のプレイヤーがどのように戦っているかを知ります。
そして最後に、その外部環境を踏まえた上で「自社(Company)」を客観的に評価するのです。
この「外側から内側へ」という視点の流れが、独りよがりな戦略を避け、市場の現実に根差した有効な打ち手を導き出すのです 。
3C分析の実践例 : 町の小さなカフェ
あなたが新しくカフェを開くと仮定して、3C分析をしてみましょう。
Customer
市場・顧客
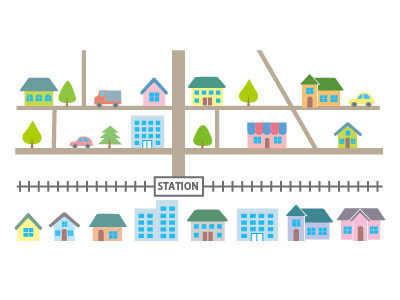
- 市場規模
駅周辺のオフィスワーカーや住民が主なターゲット。
市場は安定的 - 顧客ニーズ
平日は「手早く済ませたいランチ需要」
午後は「集中して作業したい」リモートワーカーの需要
休日は「ゆっくり話したい」友人同士の需要など、時間帯によってニーズが多様。
Competitor
競合

- スターバックス
強力なブランド力と居心地の良い空間が強み。
価格は高め。 - ドトールコーヒー
価格の安さと提供スピードの速さが強み。
長居には向かない。 - 昔ながらの喫茶店
常連客とのつながりと独特の雰囲気が強み。
新規客には入りにくい。
Company
自社
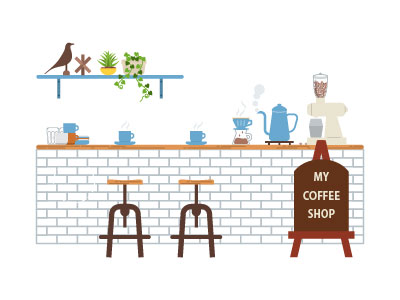
- 強み
地元の焙煎所から仕入れたこだわりの豆を使用。
静かで落ち着いた内装。 - 弱み
ブランド認知度がゼロ。
広告にかけられる予算が少ない。
この分析から、「価格やスピードでは大手チェーンに勝てない。しかし、『こだわりのコーヒーを静かな空間でじっくり楽しみたい』という特定のニーズに応えることで、独自のポジションを築けるかもしれない」という、戦略の仮説が見えてきます。
3C分析は一度行ったら終わりではありません。
顧客のニーズ、競合の動き、自社の状況は常に変化します。
定期的にこのフレームワークに立ち返り、自社の置かれた状況を再評価し続けることが、変化の激しい市場で生き残るための鍵となるのです。
第4回は、7月31日更新予定です。